就業規則の記載例88連発!
- 就業規則を見直し続けなければいけない理由
- 労働トラブルが増え、就業規則の役割が重要になってきている
- 実は会社が労働トラブルが起きるようにしていることもある
- 法改正や行政通達の動きに要注意!
- 就業規則の役割と機能
- 就業規則が労務リスクから会社を守ってくれる
- 社員が10人になったら就業規則は必要
- 就業規則には必ず書かなければならないものがある
- 就業規則は会社も拘束するものである
- 就業規則の手続きプロセスを把握する
- 労働者代表の選出方法
- 意見書は何を書くのか
- 就業規則は全部届け出しなくてもよい?
- 就業規則の届け出方法、就業規則の有効性
- 就業規則の周知は法律で決まっている
- 就業規則と労使協定の関係(1)
- 就業規則と労使協定の関係(2)
- 就業規則と労働契約の関係(1)
- 就業規則と労働契約の関係(2)
- 第1章:総則
- 目的
- 社員の定義および適用範囲
- 労働条件の変更
- 二重就業の禁止のポイント
- 第2章:人事
- 採用方法
- 入社希望者の提出書類
- 採用決定時の提出書類
- 身元保証人
- 試用期間
- 人事異動
- 降格
- 休職
- 休職期間
- 休職期間の取り扱い
- 復職
- 第3章 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労働時間(1)
- 労働時間(2)手待ち時間
- 労働時間(3)1日・1週の数え方
- 労働時間(4)行政のガイドラインを把握する
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制(1)
- フレックスタイム制(2)
- 1年単位の変形労働時間制(1)
- 1年単位の変形労働時間制(2)
- 1年単位の変形労働時間制(3)
- 休憩時間
- 休日
- 休日の振替
- 代休
- 事業場外労働みなし(1)
- 事業場外労働みなし(2)
- 事業場外労働みなし(3)在宅勤務
- 事業場外労働みなし(4)会社に戻ったとき
- 専門業務型裁量労働制(1)要件
- 専門業務型裁量労働制(2)対象業務
- 専門業務型裁量労働制(3)労使協定で定めること
- 遅刻・早退・欠勤
- 年次有給休暇(1)要件と性質
- 年次有給休暇(2)勤続年数
- 年次有給休暇(3)出勤率
- 年次有給休暇(4)事前申請
- 年次有給休暇(5)時季指定権、時季変更権
- 年次有給休暇(6)次年度への繰り越し
- 年次有給休暇(7)基準日を設けて付与する場合
- 年次有給休暇(8)計画的付与
- 年次有給休暇(9)時間単位での付与
- 慶弔休暇(特別休暇)
- 女性従業員の労働時間・休憩・休暇
- 管理監督者(1)労働時間・休憩・休日
- 管理監督者(2)管理監督者の要件
- 管理監督者(3)重要な職務内容
- 管理監督者(4)重要な責任と権限
- 管理監督者(5)労働時間の規制になじまない勤務態様
- 管理監督者(6)賃金等の待遇
- 服務規律(1)服務の原則、規律
- 服務規律(2)服務規律の変更と不利益変更の関係
- 服務規律(3)情報機器の私用禁止とモニタリング
- 服務規律(4)休日の携帯電話による業務指示への対応
- 健康診断の受診
- 疾病等による就業制限
- 懲戒の意義
- 懲戒処分の種類(1)
- 懲戒処分の種類(2)
- 懲戒処分の事由
- 懲戒処分前の自宅待機
- 懲戒処分での弁明の機会
- 懲戒処分での教唆・ほう助・加重、損害賠償
就業規則を見直し続けなければいけない理由
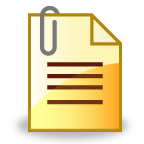 自分の会社の就業規則、見た事ありますか?
自分の会社の就業規則、見た事ありますか?
そもそも就業規則とは何なのでしょう。
労働基準法では、従業員10人以上になったら就業規則を作成し届け出なければならないとされています。
就業規則には、必ず記載されなければならない内容も決められています。
でも法律で決められているから用意するだけでいいものでしょうか。
就業規則は、会社のルールブックです。
会社と社員との間で、働く上で守らなければならない事、やってはいけない事、などのルールを明らかにしたものです。
守るべき事だけではなく、会社の考え・方針や、会社として積極的にやって欲しい事なども、しっかり伝えていくものとして上手く活用できると考えています。
会社はなま物ですから、世の中の動向に合わせて様々に変化していきます。
関係する法律も改正されたり、行政通達が出されたり、裁判の判例により解釈が変わってきたりします。
ルールブックである就業規則も、会社の方針や施策・法改正や解釈の変更に合わせて変わっていくべきものであり、変えていかなくてはいけないのです。
企業の立場からみれば、労働法令は労働者保護の立場にたっていますので、会社を守ってくれるものではありません。
しかし法律を理解し自社の運用に合わせていかないと、いつ何時、社員から訴えられるか分からないという時代にもなっているのです。
既成のもので取りあえず用意して届け出しておく、ひな型を利用して取りあえず用意しておく、では会社を守ることは決してできません。
働く社員も納得できる就業規則でないと、結局は会社を守ることもできないのです。
ぜひ会社のルールブックである就業規則を上手く活用し、会社を成長させ、社員も元気に活躍できる仕組み作りをしてほしいと考えています。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
労働トラブルが増え、就業規則の役割が重要になってきている
 ●スペシャリスト、即戦力というものの。。。
●スペシャリスト、即戦力というものの。。。
就業環境での特徴として、雇用が多様化し個別化している傾向があります。
会社としてみれば、社内事情を理解しマネジメントが得意なゼネラリストは欲しいものの、各分野で活躍して欲しいスペシャリストも求めています。
それも即戦力として期待したいのです。
現実には、即戦力として活躍してくれる社員はめったになく、多くは実力を発揮してくれるまで一定期間を必要とします。
一定期間を必要とする場合、その間に、会社の期待度にもブレが出てきますし、社員の側も「こんなはずじゃなかった」「自分はもっと活躍できるはず」と不満が溜まってくることがあります。
こういった人材に会社が対応を誤ると、さまざまな問題を引き起こす危険性をはらんでいるのです。
●非正規社員の比率が高い
雇用形態が多様化する=正社員以外に、契約社員やアルバイト・パートの活用が増えてきます。
また最近では、育児休業後に短時間社員として勤務するなど、雇用形態以外にも働き方そのものが多様化してきています。
会社は人件費を調整する方法の一つとして、正社員以外の期間雇用者を活用し、業務の繁閑に応じて対応人数を調整したり、業務内容に応じて必要スキルを保有している人材を一定期間活用したりします。
期間雇用者の中には、正社員と同じか、または正社員以上に能力もあり実際に働いているケースもあります。
そうなると、期間雇用者であるという雇用の不安を抱えつつ、一方で正社員と同じ仕事をしているのに待遇に差があると、不満を抱える者が出てきたりします。
雇用形態の多様化が進むと、会社側としては、会社固有のスキルや知識の継承ができにくくなり、職場に一体感がなくなったり、社員の流動化が進み採用コストや教育コストがかさむという問題も生じてきます。
●企業内組合の現象、ユニオン加入の急激な増加
労働組合の推定組織率は、H22年度調査で18.5%と、前年横ばい、329組合減少と減少傾向が続いています。
一方パートタイム労働者の組合員数は年々増え続け、H22年度調査では72万人が加入し、組織率も5.6%となっています。
対して、労働者個人が自由に加盟できる、いわゆる「ユニオン」は増加傾向にあり、様々な業種・業態で組合が結成されています。
これらの動きから、従来のように会社と労働組合が団体交渉によって労働条件を決定するという、集団的労使関係のシステムが機能しなくなってきており、その結果として、労働者個人が、自身で様々な知識を得て、場合によってはユニオンへ加入し、果ては労働基準監督署へ訴え出ることにより、自分の労働条件を正常化・正当化しようとしているといえます。
これにプラスして、個別労働関係紛争解決促進法や労働審判法などを施行し、行政側も労働トラブル解決の場を整備し、スピーディーに解決しようとしています。
実際に行政の紛争解決手段の利用は増えており、H22年度の個別労働紛争相談件数で24万件、あっせん申請で6400件、労働審判は3400件の申し立てが行われています。
これらいずれの場面でも就業規則が必要となり、また就業規則の内容が問われているのです。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
実は会社が労働トラブルが起きるようにしていることもある
 いろいろな考え方・価値観をもった社員、正社員・契約社員・パートアルバイトと様々な雇用形態の社員がいる職場では、通り一遍の対処だけでは労働トラブルを防ぐことはできません。
いろいろな考え方・価値観をもった社員、正社員・契約社員・パートアルバイトと様々な雇用形態の社員がいる職場では、通り一遍の対処だけでは労働トラブルを防ぐことはできません。
また労働各法に関する多くの情報や解説などが、インターネット上で、いつでもどこでも誰でも収集をし、自身に都合よく解釈し、会社に対して訴えをしてくるようになりました。
従来の考え方・価値観では、労働トラブルへの対処はできなくなっています。
とは言うものの、労働トラブルの実際では「言った・言わない」「聞いた・聞いてない」「労働条件がどうなっているのかさっぱり分からない」「就業規則にあることと実際とはまったく違っている」といった話が多いのです。
つまり、労働条件や就業ルールが適当だったり、明確になってなかったり、就業規則が手元にあっても見直しがされてなかったり、あっても社員に見せれらないものだったりという状態がために、労働トラブルが起きているのです。
社員が一方的にトラブルを起こしていると思いがちですが、会社がトラブルが起きるような状況にしているともいえるのです。
では会社はどう対処していくべきでしょう。
まずは就業規則を用意する、それも巷に出回っている「ひな型」をそのまま使うのではなく、自社の価値観や考え方を盛り込み、就業ルールを分かりやすく明確にしたものを作成する必要があります。
就業規則は法律で決まっている内容を盛り込まなくてはいけませんが、それ以外に制限があるものではありません。
堅苦しい表現では社員に伝わらないと感じた場合は、分かりやすい表現に置き換えてみたり、「です・ます調」の表現でも構わないです。
何度も言いますが、就業規則は会社のルールブックです。
「社員にはできる限り見せたくない」という就業規則では、労働トラブルが増えることはあっても、残念ながら減ることはないのです。
会社では様々な働き方をする社員を組織し、一定の秩序を保って運営し発展していかなくてはいけません。
中小企業だからこそ、社員の働き方・働く目的を明確にし、働く上でのルールを整備していかなくてはいけないのです。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
法改正や行政通達の動きに要注意!
 労働関連の法律は、世の中の動きに合わせ改正が行われます。
労働関連の法律は、世の中の動きに合わせ改正が行われます。
法律が改正されると、それまで就業規則で有効となっていた内容が今後は適用されなくなったり、知らない間に、就業規則の内容よりも法律が有利になってしまっている事があります。
法律の主旨と企業の就業ルールにズレがあったりすると、これも労働トラブルの火種になりかねません。
また重要な裁判例が出てきたときや、各法律の具体的な運用方法の行政通達も、自社の就業規則で定めてあった内容にズレが出てくる事もありますので、注意が必要です。
「とりあえず1度作っておいたから」では、現在の労働トラブルには対応できません。
新しい法律や行政通達に常に対応できているよう、定期的なメンテナンスをしなくてはならないのです。
近年の労働関連各法の法改正は、時代の流れや必要性に応じて、以下の要素・主旨に沿っていると考えます。
-
ワークライフバランスへの対応(=柔軟な働き方)
育児・介護休業法、労働基準法、労働契約法 -
雇用の確保、雇用機会の均等
男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、労働者派遣法、労働契約法、労働基準法 -
働く人の心の健康への配慮
労働安全衛生法、労働基準法
2012年は、育児・介護休業法、労働契約法、労働者派遣法、労働安全衛生法に動きがありますので、改正事項を十分に把握し、自社の就業ルールと法律との折り合いをつけていく必要があります。
育児・介護休業法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf
労働契約法
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025bjf.html
労働者派遣法
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf
労働安全衛生法
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001slsj.html
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則の役割と機能
 就業規則を見てみると、就業条件や就業上のルールが定められています。
就業規則を見てみると、就業条件や就業上のルールが定められています。
会社によって内容は異なるものの、試用期間・就業時間・休憩休日・休暇・賃金に関すること(賃金規程として別になっているのがほとんど)・退職に関すること・退職金の支給・服務規律・健康診断など安全衛生に関すること・表彰や制裁・退職や解雇・災害保障など、会社の人事労務管理に関する内容ばかりです。
つまり就業規則は「人事制度」を文書として表したものなのです。
会社の人事制度は、常に変化しています。変化に合わせて内容を見直さなければいけませんし、関係法律が改正されれば、これも対応しなければいけません。
このように常に見直しを繰り返している就業規則は、会社で働く上で守るべきルールを示したものであり「会社のルールブック」として利用されるべきものです。
最低限必要事項をまとめ条文立てて用意しておけばいいやではなく、トラブルの種が生まれないよう、実際の運用に合ったルールブックを用意することが、最低限求められるものとなります。
人事・労務管理を上手く社員にアピールし、社員を育て会社が成長しているところでは、就業規則=ルールブックを型通りに用意するのではなく、様々な場面で活用し、また積極的に活用しています。
就業規則には2つの側面があります。
ひとつは文字通りルールブックとして、法律に照らしながら、いかに自社にあったルールを明文化し、社員に理解してもらうか。
もうひとつは人事・労務管理制度をどう組み立て、就業規則を人材マネジメントツールとしてどう活かしていくべきか。
人事制度というと、人事考課・賃金制度・定年と退職金の仕組みを想像しがちですが、これらの仕組みを考えていく上では、労働関連の法律を根底に、会社の制度を考えていかなくてはいけません。
また考えられた制度は、文書化し社員に理解してもらい、実際に運用されなければ意味がなく「絵に描いた餅」で終わってしまうのです。
就業規則は、社員が働く上でのルールを理解するためのルールブックでもあり、社員を積極的に活かしていくためのマネジメントツールの役割も果たしているといえます。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則が労務リスクから会社を守ってくれる
 企業には、働く人がいる以上、多かれ少なかれ様々なリスクを抱えています。
企業には、働く人がいる以上、多かれ少なかれ様々なリスクを抱えています。
このリスクを労務リスクといい、主に以下の5つに分かれると捉えています。
1)人的リスク
社員が起こす不祥事・違反、内部情報の漏えい、人材の流出、モチベーションダウンによる企業力低下
2)費用発生リスク
未払い賃金、労働・社会保険未加入による保険料徴収
3)訴訟リスク
ハラスメントや過労死による損害賠償請求、労災隠しの告発・送検
4)行政処分リスク
許認可の取り消し、一定期間の業務停止命令
5)風評被害リスク
法令違反による企業名公表や、インターネット上での書き込みなどによる信用失墜・イメージダウン
就業規則は、これらの労務リスクを抑制し管理する機能を担っています。
就業規則が会社のルールブックだからといって、何でも好きに定めても良いというものではなく、関係法令に則って作成することが求められます。
関係法令に基づいてルールを作成し、そのルールが会社の運営上にどのような影響を与えるのかを常に考える=コンプライアンスリスクへ対応していくことにつながっていきます。
ルールブックの機能としては、社員に守って欲しい事・やってはいけない事を明確にし、社員に周知していくというのがあります。
これにより社員の不祥事を未然に防ぐ、ルール違反をした際には明確で客観的な処分をすることにつながっていきます。
一方で、ルールブックである以上は、会社も就業規則を守らなければいけません。
関係法令に基づいて定められた就業規則を用意するという事は、会社に法令順守を強いているといえ、長時間労働や未払い残業代、ハラスメント行為などを防止する意味が含まれています。
このように就業規則は、会社の諸事情や就業環境を十分に考慮した上で準備がされていれば、会社が抱える労務リスクを直前のところで防いでくれるものといえます。
就業規則が持つ役割と機能をしっかり理解し、自社の就業規則をより良く・上手く活用できるものとして整備をしていただきたいと思っています。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
社員が10人になったら就業規則は必要
 労働基準法第89条には「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とあります。
労働基準法第89条には「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とあります。
これは就業規則を作成もしなければならないし、届け出もしていなければならないという事です。
就業規則を作成はしているものの届け出していなければ、やはり労働基準法違反になります。
では、この「常時10人以上」はどういった状況を表すのでしょう。
まず人数には、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども含まれます。
派遣社員は、派遣元企業の労働者として数えますので、派遣先では労働者数に含みません。
「常時」の状態については、一時的に10人未満となった場合でも、採用募集を行い補充を考えているような場合は「常時10人以上」とします。
逆に、普段は10人未満であるものの、業務量の増加により一時的に従業員を補充し10人以上の状態であったとしても「常時10人以上」であるとはしません。
また就業規則を準備する場合「事業所単位」で作成することとされます。
この事業所単位とは「1企業=1事業所」という事ではなく、本社以外に働く場所がある場合には、例えば支店・店舗・工場など各々の場所単位で作成するものとされます。
ただ本社以外に複数の就労場所があった場合でも、本社と同じ就業規則が適用されるというときは、本社と一括して届け出を行うという方法もあります。
さて「常時10人以上」の労働者がいない場合は、就業規則は本当に必要ないのでしょうか。
この場合、就業規則が作成されていなくても、労働基準法上での違反を問われることにはなりません。
社員ごとに労働・雇用契約書を取り交わしているし、契約書内に就業条件が定めてあり内容にも問題がないのであれば、確かに事は足りるともいえます。
ただ労働・雇用契約書だけでは会社の姿勢やルールを伝えきれるものではありません。
将来に向けて会社を成長させたい、社員に持てる力を発揮してもらいたいと考えているのであれば、今は10人未満の社員であったとしても、就業規則の本来持つ役割と機能を活かし、会社のルールブックとして活用していくためにも、会社の姿勢やルールを示した就業規則を準備していくべきではないでしょうか。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則には必ず書かなければならないものがある
 就業規則を作成するとき、あるいは今あるものを見直すときに、就業規則に必ず定められていなければならない事項が書かれているか、また書かれている内容に問題はないか確認をします。
就業規則を作成するとき、あるいは今あるものを見直すときに、就業規則に必ず定められていなければならない事項が書かれているか、また書かれている内容に問題はないか確認をします。
これは、必ず記載されていなければならないもの=絶対的記載事項と、会社がルールを設けた場合には記載しなければならないもの=相対的記載事項とに分かれます。
【絶対的記載事項】
1.労働時間に関する事項
・始業、終業の時刻
・休憩時間
・休日
・休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
・交替勤務がある場合は交替勤務のルール?
2.賃金に関する事項
・賃金(基本給や各手当)の決定方法、計算方法
・賃金の支払い方法
・賃金の締切日と支払日
・昇給について(時期、方法など)
3.退職に関する事項
・退職、解雇、定年となる理由
・退職、解雇、定年の際の手続きなど
【相対的記載事項】
1.退職金に関する事項
・支給される対象者
・金額の決定方法、計算方法
・支払方法
・支払時期
2.賞与に関する事項
・従業員の食費、作業用品その他の負担に関する事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償と業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰と制裁の種類、それぞれの事由に関する事項
・その他従業員の全てに適用される事項?
絶対的記載事項は、その名の通り、必ず就業規則に定めておかなければいけません。
絶対的記載事項とされる内容は、どの時間働けばいいのか、いつ休みがとれるのか、給与はいつ・どんな形で支払われるのかという、具体的に決まっていないと社員が働く上で(労務を提供する上で)困ってしまうものを指しています。
同様に、退職するときや解雇となったときも、どういった方法で退職の手続きをすればいいのか、解雇となる理由にはどういったものがあるのかなどが決まっていないと、会社と社員との雇用契約を解除する際にトラブルになりかねませんので、絶対的記載事項に含まれています。
対して、相対的記載事項は、会社のルールとして定めるのであれば就業規則にも記載をしなければならないものとされています。
制度がないのであれば、記載する必要はありません。
例えば、退職に関する事項は、労働者を雇用している以上は必ず起こることですので、どういう手続きをするのか、退職となる理由にはどういうものがあるのかを定めておく必要があります。
一方で退職金を支給するかどうかは会社によって異なりますので、退職金を支給するのであれば、どういう場合に支給されるのか、支給される額はどの程度なのか、どういう形で支給されるのかなどをルール化しておかないと、個人事情に左右されたものとなってしまいます。
また退職金は制度化された場合に「賃金債権」となりますので、トラブルにならないためにも就業規則にルールを定めておく必要があります。
元々、労働基準法は昭和22年に施行された法律で、終戦後早い段階で施行された法律です。
古くから徒弟制度などが一般的であった日本では働く側の権利が圧倒的に弱く、中間搾取なども当たり前に行われていたところを、法律で労働者を守ろうという背景からスタートしていますので、労働基準法は労働者保護の立場にあるものといえます。
最後に、就業規則には、上記の絶対的記載事項・相対的記載事項の他に、任意的記載事項というものがあります。
これはどういった内容を定めても構わないもので、第1章(総則)として社是や社訓・就業規則の目的を定めているものが該当します。
総則以外にも、会社独自のルールがある場合はそれを記載する、他にも小売業など接客がメインの業種では、接客時の心構えやマナーなどをあえて就業規則に記載したりすることもあります。
就業規則を自社に合ったものとする、ルールブックとして活かすには、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項のどの項目に該当するものが定められているのか、制限されている項目に漏れや不十分なところはないか、会社のルールが明確になっているか、などを常に考えながら行っていく必要があります。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則は会社も拘束するものである
 就業規則の作成・届出義務は会社にあります。
就業規則の作成・届出義務は会社にあります。
法律で定められた内容は当然の事ですが、法律で定められていない内容をルール化するには、就業規則に定める事で有効となります。
就業規則に定めた就業条件は社員だけを拘束するものではなく、会社も拘束されるものです。
つまり就業規則に定められていない事は、原則としてやってはいけない事になります。
これは前述の絶対的記載事項・相対的記載事項のいずれも当てはまります。
例えば、始業・終業時刻として、9:00~18:00(休憩は60分)と定められていた場合、18時以降は働かせてはいけません。また休憩も60分与えなければならないのです。
そうはいっても18時以降も仕事をしなければいけない場合もありますし、就業時間を変更する必要がある場合もあります。
そういう時のために、36(サブロク)協定を締結し労働基準監督署へ届け出することで、一定の制限の下で残業をするものとなります。
同様に就業時間を変更する必要が出る時に備えて、就業規則内に「業務上の都合により、就業時間を変更し、始業時間を繰り上げ、または繰り下げる場合がある~」などと定めておきます。
解雇なども同様です。
就業規則に解雇や懲戒処分に関する定めがなければ、たとえ社員の取った行動が原因で会社に著しい損害を与えたとしても、懲戒処分とする事もできず、果ては解雇理由に該当するとしても正当な理由ではないと解雇もできないとなります。
就業規則を定めた会社も拘束される、社員へは会社のルールを示し説明責任を果たすという点において、就業規則は中小的すぎず、細かすぎず、適当な頃合いをもって定めておく必要があるといえます。
これから就業規則を作成する、または今の就業規則を見直すという場合に、自社の就業規則が効果があり有効なものとしていくためにも、今後お伝えしていく「条文別記載例とポイント」をぜひ参考にしてください。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則の手続きプロセスを把握する
 就業規則は、従業員数が常時10名以上になったら作成し、労働基準監督署へ届け出なければいけません。
就業規則は、従業員数が常時10名以上になったら作成し、労働基準監督署へ届け出なければいけません。
これは労働基準法第89条に定められてあり、企業に義務を課すものです。
具体的には、以下の流れで行っていきます。
1)就業規則案を会社で作成する
- 現行の課題を確認
- 作成スケジュールを検討
- 労働条件の異なる社員を分類し定義付けする
- 企業の経営理念や経営方針から就業規則に盛り込む内容を確認
- 現行の労働条件が各法令に違反していないかチェック
2)過半数組合または労働者の過半数代表者への説明・意見聴取
- 労働者の過半数が所属する労働組合がある場合は、その労働組合へ説明し意見聴取
- 労働者の過半数が所属する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者へ説明し意見徴収
3)労働基準監督署へ届け出
- 上記の意見を意見書へ記入し署名、または記名押印をしてもらう
- 就業規則届(変更届)を用意し届け出する就業規則と合わせて提出
4)決められた方法で社員に周知する
次のいずれかで周知
- 常時見やすい場所に掲示するか、常備しておきいつでも見られるようにする
- 就業規則そのものを配布する
- グループウェアや共有サーバー等に就業規則データを保管しておき、いつでも内容を確認できる状態にしておく
次回は、上記の流れに沿ってポイントを説明していきます。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
労働者代表の選出方法
 就業規則の届け出にあたり、必ず聞かれるのが「労働者代表」をどうやって選べばいいのか?です。
就業規則の届け出にあたり、必ず聞かれるのが「労働者代表」をどうやって選べばいいのか?です。
社内に労働組合があるケースというのは限られており、多くの企業では社員の中から労働者代表を選出しなければいけません。
まず労働者代表になるには条件があります。
ひとつは、労働基準法41条2号に該当する「管理監督者」ではないこと。
これは労働基準法でいうところの管理監督者であり、役職名で判断するものではありませんが、例えば課長職以上は管理職としている=管理監督者であると会社で定めている場合には、課長職以上の社員を除いて代表者を選出することとなります。
2つめは、就業規則の作成・変更にあたり会社から意見を聴かれる者を選ぶとした上で、それぞれの方法により選出される必要があります。
そうはいっても、社員から自主的に労働者代表を選ぶという事はやりにくいため、会社が社員から依頼された事を明らかにした上で、代表選出の方法や具体的な手続きを代わって行うのは可能です。
多くの会社では、会社側が労働者に代わって選出手続きを行っています。
選出にあたり、下記の方法では、代表が選出されても無効とされますので注意が必要です。
1)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
2)親睦会の代表者が自動的に労働者代表となっている場合
3)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
4)一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出している場合
では具体的にどのような方法で労働者代表を選出するのでしょうか。
一例として、以下の方法もあります。
- 社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
- 自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて賛成・反対の意思表示をしてもらう
- 過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する
ちなみに選出方法について、行政通達では「労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的手続が該当する」とされています。
さて代表選出の方法は理解できたとして、過半数となる「母数」はどうやって決めるのでしょう。
この母数の定義は法律で明確に定められてなく、行政解釈(S46.1.18基収6206号、S63.3.14基発150号、H11.3.31基発168号)では、労働基準法第9条の定義によるのが妥当とされています。
労働基準法第9条「業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」である、管理職を含め、ほぼすべての従業員が対象になるというわけです。
つまり上述の通り、管理監督者は過半数代表者には選出できませんが、全労働者数には含みます。
行政通達では、役職名が管理職であったとしても労働時間管理をしている場合には、労働者代表の選出権があるとされています。
こういった場合、管理監督者を除いた社員全員により過半数代表者を選出してたとしても、選出された人物は過半数代表者とはなりませんので注意が必要です。
以上より、労働時間の規制のない管理監督者としている者、年少者、育児・介護休業者、出張中の者、長期欠勤、休職者、出向者など、在籍している全ての方を「労働者の過半数」の算定に入れるべきだとされています。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
意見書は何を書くのか
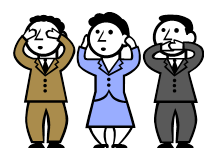 作成・変更した就業規則を労働基準監督署に届け出る際に「意見書」を添付します。
作成・変更した就業規則を労働基準監督署に届け出る際に「意見書」を添付します。
これは労働者の過半数代表者より就業規則に関する意見を聴いたとの証明をするもので、意見を記入してもらい、署名か記名押印をしてもらいます。
労働者の過半数代表者より意見を聴くがポイント。
「聞く」ではなく「聴く」という定めになっています。
どういう事かというと、過半数代表者に就業規則の内容に「同意」してもらう事を求めているのではなく、賛成できる点もあれば、反対する点もあるという意見を率直に記入してもらえばよいのです。
中には、法律に違反していないものの、もっと良い労働条件にして欲しいという意見が出てくる場合もあります。
様々な意見が出て、仮に反対されたとしても、これをもって新しい就業規則を直ちに変更する必要はなく、就業規則の効力にも影響はありません。
では、意見書そのものの提出を拒否された場合はどうなるのでしょう。
この時は、使用者側(会社)が過半数代表者に意見を聴き、意見書への記載・署名を求めたものの拒否されたという事実を書面で用意し、就業規則作成(変更)届に添付して届け出すれば、法律上の問題は問われない事となります。
実際に上記のような状況になるとすれば、意見書の提出そのものを拒否するという社員との関係性に、そもそもの問題点があるわけで、就業規則の作成以前に、会社と社員との関係回復・良好な関係へ改善する事が先に行われるべきといえます。
就業規則(変更)届
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/11.doc
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/11.pdf
就業規則意見書
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/12.doc
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/12.pdf
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則は全部届け出しなくてもよい?
 一般的に、就業規則とは別に、賃金規程・退職金規程・出張旅費規程など、いくつもの規程が用意されています。
一般的に、就業規則とは別に、賃金規程・退職金規程・出張旅費規程など、いくつもの規程が用意されています。
これは就業規則に全部の内容を盛り込んで就業規則そのものが分かりにくくならないようにするのと、見直しや修正がしやすいようにするために、通常はそれぞれの内容に応じて分けて定めておきます。
この場合、賃金規程や退職金規程など就業規則内で「別に定める賃金規程により支給する」など、別規程で規定されていると記載をします。
出張旅費規程など、就業規則に直接関連性はないものの全社員に適用されるものについては、個別に規程を設けていきます。
いわゆる細則とされるものになります。
就業規則を届け出る際にどこまで届け出しなければいけないのでしょう。
結論からいくと「すべての労働者に適用される事項、または労働者のすべてに適用される可能性がある事項については就業規則への記載が必要であり、別規程を作成する場合は、その規程も含めて就業規則となる」という点です。
行政通達(S25.1.20基収第3751号、H11.3.31基発第168号)では、旅費に関する一般的規定をつくる場合には、労働基準法第89条第10号により就業規則の中に規定しなければならないとされ、出張旅費に関する規定も就業規則に定めなければならないとされているのです。
全社員に適用されるものは当然のこと、一部の社員についてのみ適用される規程は、例えば福利厚生的なものであっても就業規則と一緒に届け出しなければいけないとなります。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則の届け出方法、就業規則の有効性
【今日のポイント】
- 就業規則の届け出は「事業所単位」が基本
- 届け出されていない就業規則は、労働基準法に違反しているが、原則として有効性がある
 作成・見直しされた就業規則への労働者代表からの意見書を提出してもらったら、労働基準監督署へ届け出をします。
作成・見直しされた就業規則への労働者代表からの意見書を提出してもらったら、労働基準監督署へ届け出をします。
届け出る際には、次のものを揃えます。
- 就業規則作成(変更)届
- 労働者代表の意見書
- 就業規則(別規程も含む)
就業規則作成(変更)届の様式は決められていませんが、各都道府県労働局にダウンロードサンプルが用意されています。
参考)東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/11.doc
初めて就業規則を作成した際は、全文を添付し届け出します。
見直しによる変更の際は、変更部分の新旧対照表を用意し、これに変更された就業規則を合わせて届け出しても良いですし、変更された就業規則全文を届け出ても構いません。
届け出は「事業所単位」となります。
ここでいう「事業所単位」とは、本社・支店・支社・店舗・営業所など、労働者が実際に就労している現場単位となります。
ただし、これら複数の事業所で同じ就業規則が適用される場合には、本社で一括して届け出を行う事ができます。
本社で一括し届け出を行う場合には、対象となる事業所数の就業規則を用意し、各事業所ごとに労働者代表の意見を聴き意見書を用意する必要があります。
また就業規則の届け出にあたり、届け出されていない就業規則は有効なのかどうか質問が多くされます。
これについては、届け出されていない事そのものは労働基準法に違反しているものとなりますが、労働者代表の意見を聴き、就業規則の周知もされているようであれば、就業規則の効力自体には影響はないとされています。
ただ会社を成長させていくためにはコンプライアンスは基本であり、届け出がされていない状態であれば、すぐにでも対処すべきといえます。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則の周知は法律で決まっている

【今日のポイント】
- 周知する方法は法律で決まっているものから選ぶ
- 社員全員が「どこに就業規則があるか」を理解していること
労働基準監督署に届出をした就業規則は、社員全員が確認できるよう「周知」をします。
※周知=広く知らせること
この周知する方法については、会社が独自に決めたものでいいのかというと法律で定められています。
労働基準法施行規則第52条の2
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
これら3つの方法から会社が周知しやすい方法で行う事となります。
「常時各作業場の見やすい場所」は、社員が自由に確認できる場所に設置しておきます。
総務部のカギのかかる書棚に入ってるとか、上司の机の引き出しにしか入っていないとかは「×」です。
「書面を労働者に交付する」文字通り、印刷した就業規則を手渡しすることになります。
この方法を取る場合は、ナンバリングをし退職時に返還してもらうなど、会社によって管理方法が異なります。
「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し~」は、就業規則をPDF化し社内の共有サーバーやグループウェアで自由にいつでも見られる状態にしておき、かつ、保管場所を社員が把握しているようになっていることになります。
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則と労使協定の関係(1)
【今日のポイント】
- 労使協定は締結するだけで良いものと、労働基準監督署に届出が必要なものとがある
- 労使協定は事業場すべての労働者に適用されるが、労働協約は締結する労働組合員に適用される
 就業規則を作成・見直しすると、定められた就業ルールによっては労使協定が必要なる場合があります。
就業規則を作成・見直しすると、定められた就業ルールによっては労使協定が必要なる場合があります。
労使協定とは、文字通り「労働者」と「使用者」との間で就業条件等に関して協議をし、協議した内容を書面にし取り交わしをした約束事です。
ここでの「労働者」は、いわゆる「事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者」になります。
労働組合がある場合は、労働組合と交渉をした内容を書面にします。
労働組合との間で締結されたものは「労働協約」といい、締結された内容が適用される範囲は労働組合の加入員となります。組合員以外には適用にならないのです。
ただし、事業場の労働者の多数を占める労働組合と締結された労働協約は、組合員以外にも適用されることもあります。
労使協定は労働者の過半数代表者と締結しますので、締結された内容は、その事業場全体に適用されるものとなりますが、労働協約は労働組合と締結しますので原則的には組合加入員に適用されるものとなります。
労使協定は、締結する内容を有効にするために取り交わせばいいものと、締結した内容を労働基準監督署に届け出て有効となるものとに分かれます。
以下、届出が必要な労使協定となりますので、労使協定を締結したら忘れずに届け出を行ってください。
- 貯蓄金管理に関する協定(労働基準法第18条)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(労働基準法第32条の4)
- 1か月単位の変形労働時間制に関する協定(労働基準法第32条の2)
- 1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定(労働基準法第32条の5)
- 時間外・休日労働に関する協定(労働基準法第36条)
- 事業場外労働に関する協定(労働基準法第38条の2)
- 裁量労働に関する協定(労働基準法第38条の3、第38条の4)
就業規則に関する「社員も安心、会社も納得の就業規則ページ」も是非ご覧ください。
就業規則と労使協定の関係(2)
労使協定と労働協約の関係について。
【今日のポイント】
- 労使協定は労働基準法を根拠とするもので、労働者と使用者との間の約束事。協定の締結を要件に「労働基準法に違反しない」という免罰(罰を免れる)効果がある。労働基準法の要求する事項に限られる。
- 労働協約は労働組合法を根拠とするもので「使用者と労